「それって考えすぎじゃない?」
そんな言葉に違和感を持ったことがあるあなたへ
自分ではただ丁寧に考えているだけ。
適当に決めたくないから、少し立ち止まって考えているだけ。
でも、なぜかその姿勢は「慎重すぎる」だとか、「面倒くさい」なんて受け取られてしまう
言ってくる側に悪気がないことはわかっているけど、「早く動けることが正しい」という前提が静かに存在している
私は考えすぎることが悪いことだと思っていないし、
それでも考えすぎて苦しくなってしまう瞬間もちゃんと知ってます
この記事では、なぜ私たちが考えすぎてしまうのかをMBTIの視点を交えながら分析してみます
もしあなたが考えすぎていることで自分を責めているのなら、ここで少しだけ「考えること」について考えてみませんか
なぜ考えすぎてしまうのか
考えすぎてしまう理由は、大きく分けて「心理的要因」と「性格的要因」の2つがあると考えています
心理的要因には、過去の経験やトラウマ、不安傾向、HSPのような感受性の強さなどが含まれます
これらは人によって背景が大きく異なるため、深くは触れません
今回注目したいのは性格的要因、つまり「考える傾向そのものを性格としている人」の方です
例えば、
- 物事を構造的に捉える癖がある
- 複数の可能性を同時に検討する
- 矛盾を抱えたまま保留できる
などと言った思考スタイルです
この記事では、こうした思考の癖としての考えすぎに焦点を当てて、タイプごとにどんな傾向があるのかを整理していきます
「考えるのが楽しいタイプ」と、「不安で考えてしまうタイプ」
考えすぎてしまう性格と一言で言っても、なぜそのように思考を重ねてしまうのか
その理由は、さらに2つに分けられると考えています
ひとつは、考えることそのものが楽しいタイプ
もうひとつは、考えないと不安で仕方がないタイプ
どちらも思考のスタート地点は違いますが、共通しているのは「思考に時間がかかる」という点です
そして、その時間ことが周囲からは「止まっている」「迷っている」と誤解されやすい要因になっているのです
もしあなたが、自分はなぜここまで考えることにこだわっているのか気になっているのなら
より深い内面の動機を探るヒントとして、エニアグラムの視点も参考になるかもしれません
なぜ、自分がそうなるのか。深掘りしたい方はこちらの記事をご覧ください
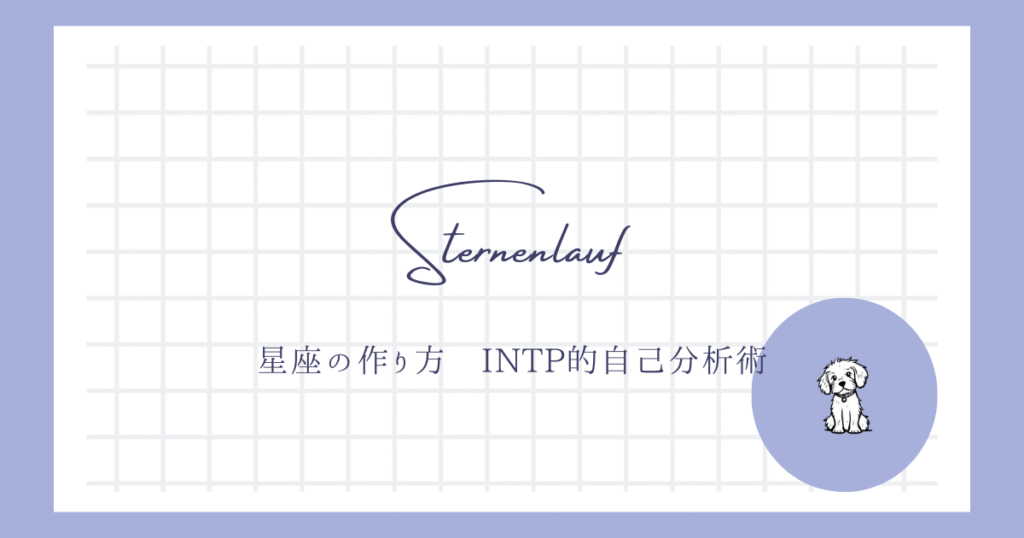
考えるのが楽しいタイプ
このタイプの人は、考えること自体が目的になっていることが多いです
何かを決めるために考えるというよりは、問いを深掘りしていく過程にこそ魅力を感じています
例えば
- 「これって、そもそもどういう仕組みなんだろう?」と興味本位で掘り下げたり
- 「一応結論は出たけど、もう少し別の視点からも見ておきたい」と、あえて遠回りしたり
- 「結論よりも、矛盾を抱えながら思考を保留すること」に抵抗がなかったり
そうした傾向があり、まるで思考することが娯楽や、習慣のように根付いているのが特徴です
このタイプは、本人から見ると「考えすぎているように見えるけど、本人はむしろ楽しんでいる」ケースが多く、そもそも考えすぎという自覚がないことさえあります
不安で考えすぎてしまうタイプ
一方で、「考えないと不安になる」タイプの人もいます
このタイプにとって、考えることは楽しいというよりも安心するための手段です
例えば
- 何かを決めようとしても、「本当にこれで大丈夫かな?」と、繰り返し確認してしまったり
- 予測できない状況が怖くて、起こりうるリスクを片っ端から想定したり
- 「最悪のケースを考えておかないと、後悔するかも」と、思考が止められなかったり
このように、不安を消すために思考を重ねる傾向があり、結果として思考時間が長引いてしまいます
本人も考えすぎだと自覚していることが多く、止めたくても止められない葛藤を抱えがちです
周囲からの「もういいじゃん」「悩みすぎじゃない?」という言葉で、さらに落ち込み考え込んでしまうことも少なくありません
簡単に言ってしまえば、考え出すきっかけが、好奇心ベースか不安ベースかであることが多いのではないかということです
どちらのタイプにせよ、思考のスタート地点は人によって異なります
もしあなたが「自分はなぜ、ここまで考えることにこだわってしまうのか?」と気になったのなら、より詳しい動機を探るヒントとして、エニアグラムの視点も参考になるかもしれません
周囲との価値観の違い
こうした「思考に時間をかけるタイプ」の人たちがぶつかりやすいのが、スピード感や正しさに対する価値観の違いです
多くの人にとって、行動こそが結果を生み出すものです
「悩んでいる暇があったら動いた方がいい」
「まずやって見て、ダメだったらその時考えればいい」
そんなふうに、行動が正解だと信じる文化の中では、考える時間が長い人は「ただ無駄に迷っている」「行動が遅すぎる」とみなされがちです
けれど、考えることを必要としている人にとって、行動とは思考をした後の工程であり、そこに至るまでのプロセスを丁寧に積み上げないと、安心して前に進めないのです
このすれ違いは単なるテンポの違いではなく、「安心の感じ方」「納得の基準」の違いでもあります
どちらが正しい、間違っているという話ではなく、価値観の軸そのものが異なっている
だからこそ、理解しあうには、少しの時間と歩み寄りが必要なのだと思います
考えすぎは本当に短所なのか?
「考えすぎ」という言葉は、大抵ネガティブな意味で使われています
まるで、「迷っていて動けない人」「余計なことばかり気にする人」だとみなされてしまう
けれど本当に、「考えすぎること」は短所なのでしょうか?
ここでは、考えすぎが短所に見えやすい理由と、その裏にある可能性について、少し視点を変えて考えて見たいと思います
決して正当化をするためではなく、考えることに意味を感じながらも傷ついてきた私から、同じことで悩んでいる方々のためにです
短所に見えやすい理由とその裏にある強み
考えすぎることが短所扱いされてしまう背景には、行動を重視する文化的価値観があります
- 「すぐに決められる人」が できる人
- 「悩まずに動ける人」が 前向きな人
- 「迷わない人」が 信頼できる人
このような評価軸の中で「一度立ち止まって考える人」「何度も検討し直す人」は、非効率で優柔不断な人だとラベリングされてしまいがちです
でも裏を返せば、それはすべて「慎重である」「物事を多方面から見ることができる」「リスクを予測することができる」ともいえます
行動前に思考を重ねることは、破綻を未然に防ぐ力であり、短期的にはわかりづらくても、長期的には大きなミスを避ける強みになっていることが多いのです
つまり、考えすぎることが評価されにくいのは、その価値が見えにくい構造にあるだけで、本質的に思考する力が備わっている証でもあるのです
INTPとして感じる思考の深さの価値
私自身、INTPという典型的な考えすぎなタイプとして生きてきた中で、数えきれないくらい考えすぎだ、もっと感覚で動くべきだと言われてきました
でも私にとって考えることは、単なる手段ではなく、それ自体が自己表現であり、安心するための手段であり、娯楽でもあります
矛盾があってもその問いを考え続けること。
明確な答えが出なくても、納得できるところまで掘り下げること。
結論がいくつも同時に存在している中で、どれも正解でいいじゃんと思えること。
それらはすぐに答えを出すこととはまた違った意味で、人間的な深みや知性、そして柔らかさを養ってくれるものだと私は信じています
もちろん、考えすぎた結果、動けなくなってしまうこともあります
でもそれすらも、自分の中に腑に落とすために必要な時間だったと思えるようになりました
考えるという行為に対して、自分自身が価値を見出しているかどうか
それが、自分にとって考えすぎてしまうことが短所なのか、財産なのかを分ける基準なのかなと考えました
noteでこの記事に関連した深掘りを投稿しました
お時間がありましたあ、ぜひ合わせてご覧くださいね〜


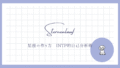

コメント